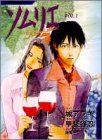D
推理物でいう“最後の一行”物を“最後の一枚物”に変えただけで、絵である必要性の薄い話ばかり。『しあわせの書』のように成立させたことを褒めるほどでもなく、発想自体もそうおもしろくはない。
読み物としても全体的に長ったらしく、削りに削れば4コママンガにできるのではというものすらある。
おまけにオチは予想外なのにおもしろくないというなんとも残念なものが少なくない。
D
前作『厭魅の如き憑くもの』はホラーとして楽しんだが、今作はまったく怖くない。事象をロジカルに捉えて進むうえ、怖がらせようという意思そのものを感じなかった。
また前作では雰囲気作りに一役買っていた土着信仰描写も蛇足感が強まる。
おまけにトリックには無理がある。チベットの例を出していたけどあれは解体してあの時間なのであって、そのままの場合完遂できるかどうかすら怪しい。
あと、やはり地形図は欲しいところ。
D
前半は『しあわせの書』『生者と死者』のようなおもちゃ短編集。
『カヴス・ガヴス』はよくやるなと感心した。 逆に『お薬師様』は混ぜこぜにした話を2周目で時系列順に読ませるだけでちょっと残念。
一方、後半は『まだ旅立ってもいないのに』のような意味不明さ。
実験的という意味では十分だが、読み物としておもしろいかは少々微妙。“思いつき”を作品として楽しめる“アイディア”にまでもっていけてない面もあると思う。
厭魅の如き憑くもの/三津田 信三
C
『鴉』を彷彿とさせる濃厚さ。
夜道を一人歩くような言いようのない不安で不気味な雰囲気はみごと。物語への没入度が高く、自然そこで語られる怪異も怖さを増す。
ただ、言葉尻をtpらえるような細かい複線は読者に自主的に気づかせるべきであって、本編で堂々と出すならもうちょっとパワーが欲しかったか。
また、村の歴史などはよく考えたなと感心させられる反面、それ本筋に関係あるの?と説明の長さに平行させられる。
C
あいかわらずキャラ描写は上手(『彼女が死んだ夜』のタックシリーズを思い出す5人だ)。
が、ストーリーが他愛なさすぎ。事件は起きているが、フィクションとしては平凡すぎる。さりげなく伏線を引いて、爽快な回収というのも一応やってはいるが歴代作品に劣る感じ。
最近、伊坂作品を読むと上記したような感想ばかり浮かぶが、単に私が飽きてきただけなんだろうか。
あと、P283の売れる小説どうこうはスタンスの表明って事でいいのかね。『オーデュボンの祈り』でも寓話について似たような事を書いてた気がするし。
D
ゲーム版の良さが選択肢による展開の多様さだったため、そういう意味ではややハンデを抱えている作品。
高木ババアの話は丈の長さ相応に楽しませてくれたが、他はイマイチ。 小説ならではの表現を気にするあまり過激な描写ばかりが目立ち、恐怖という要素が薄く感じた。
また、語り手の性格も変わっており話している様子がイメージしづらい(荒井の「ひひ……」はちょっとね)。
ゲームからそのまま持ってきたような文章で情景描写も薄め。
あと、風間の話はもう少し短くならなかったのか。
B
初めて読んだ時は素直に驚いたが、改めて読むと見事なまでのバカミス。
だが、それでも『ぼうぼう森、燃えた』の秀逸さは色あせない。1話目でやられて地団太を踏んでいる読者の足下にビー玉を転がすような憎たらしさ。
ただ、全編通して内輪ネタの気があり、U君の正体が過去の作者などわかりっこない。本来なら解説がその辺りをフォローしてくれるのだが、残念ながら本書解説はその用を為していない。
しかし、『名探偵の掟』といい、この手の悩みは推理作家共通なのか。
D
きちんと物語にけりをつけただけ前作(『『クロック城』殺人事件』)よりは評価できるが、できの悪いラノベのような内容はあいかわらず。読み始めて作者の筆力にげんなり、慣れた頃にスノウウィのきざなセリフにまたげんなり。
SF設定をルール付けなしで城のトリックに使ってしまったのも×。最後のオチに使うだけなら良かったのだが。
トリック自体は私がこの手のものが苦手なので客観的に評価はできないが悪くないと思う。
あと、これとネタが被っているような気がするが…よくあるものなのか?
稀に見る傑作。
A
おもしろい。
B
まあまあ。
C
標準ランク。人によってはB。
D
微妙。
E
読むのが苦痛なレベル。
F
つまらないを越えた何か。
×
エックスではなくバツ。よほどアレでない限り使わない。